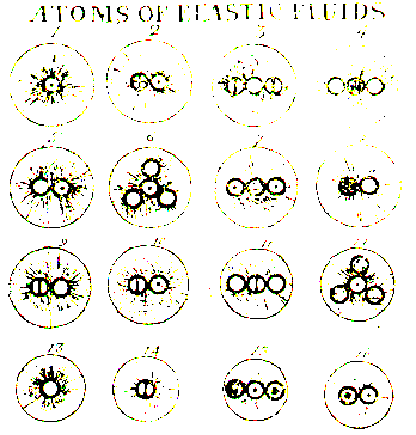
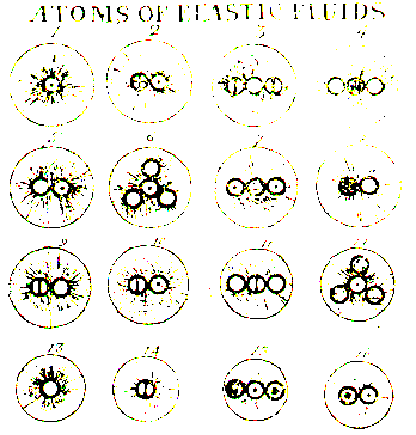 |
産業革命期は、蒸気機関改良の理論的基礎として、熱学の研究が盛んであった。それでは、当時熱とはいかなるものであると考えられていたのだろうか。熱は「熱素」(caloric)という重さのない弾性物質であって、その粒子は相互に反発し、他のすべての物質からは強く引かれていると考えられていた。この考え方が熱素説である。この考え方を使ってほとんどの熱現象が説明できたので、一般にこの説が信じられていた。今日熱量をはかる単位としてカロリー[cal]が用いられているが、これは熱素説に由来するものである。左図は熱素圏に取り巻かれたドルトンの原子である。
|
実験1.
2つの同じ大砲に等量の火薬を使用し、一方にはア弾丸を込め、他方にはイ弾丸を込めずに発砲した。このときの砲身の熱さを比べる。
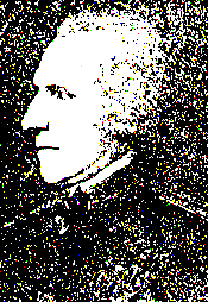 |
◇ランフォードの実験予測(推論) 砲身の加熱は、熱素説に従えば火薬の発熱に基づくと考えられる。したがって、弾丸を込めて発砲するときの方が、火焔が砲身内に長く閉じこめられていることになるので、砲身はより熱くなると考えられる。 |
Q4.ランフォードの実験予測は、熱素説の立場にたって行われた。この立場に従えば、ア、イ、どちらの場合がより熱くなると考えられるか。
◇実験事実
| 弾丸を込めなかった方が込めた方に比べて、ずっと熱くなった。 |
この実験事実からランフォードは、上記の実験予測の推論は誤っていると考え、この実験事実を説明するために次のように推論を訂正した。
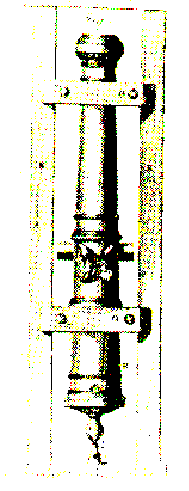
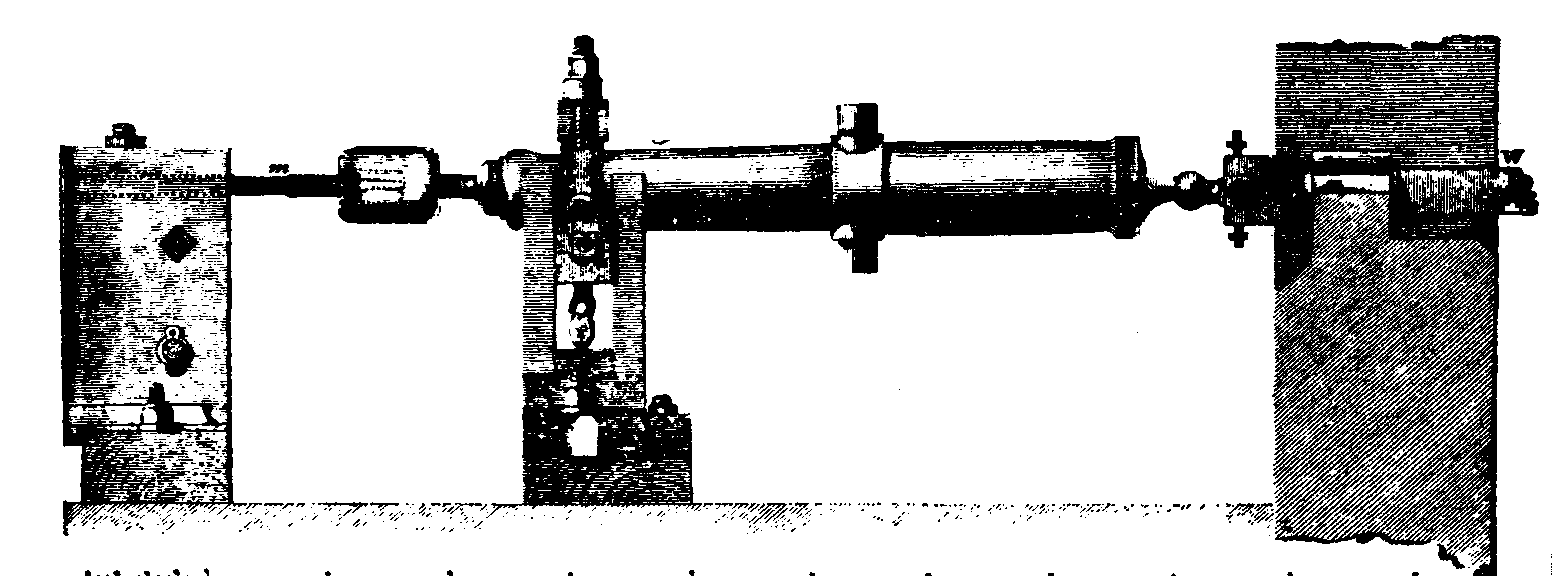
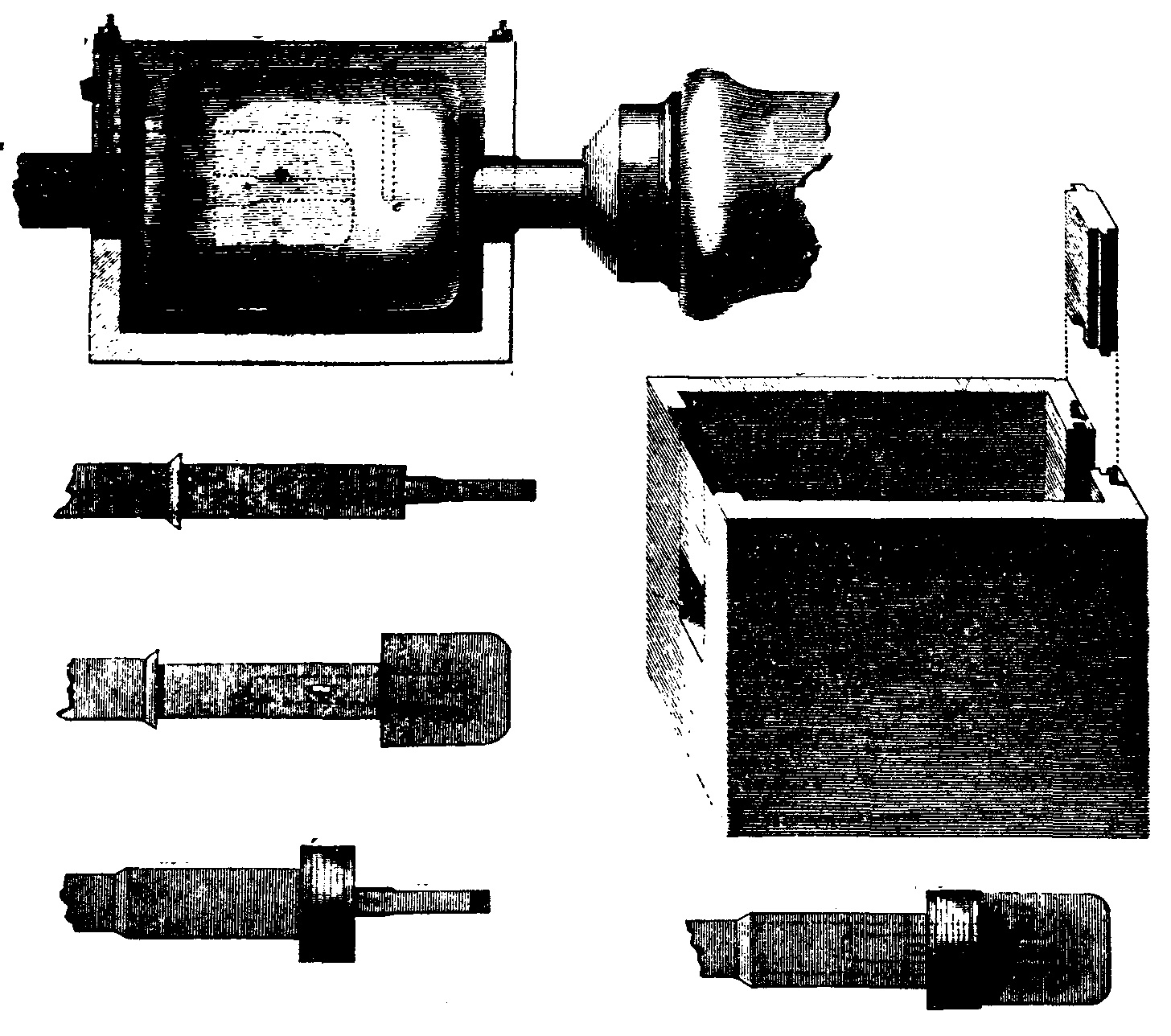 |
ランフォードは、この実験事実を次のように説明した。
◇ランフォードの推論
|
ランフォードは次のように結論した。
◇課題実験1
摩擦によって熱が出てくることを確認する実験を考えよ。