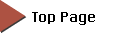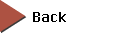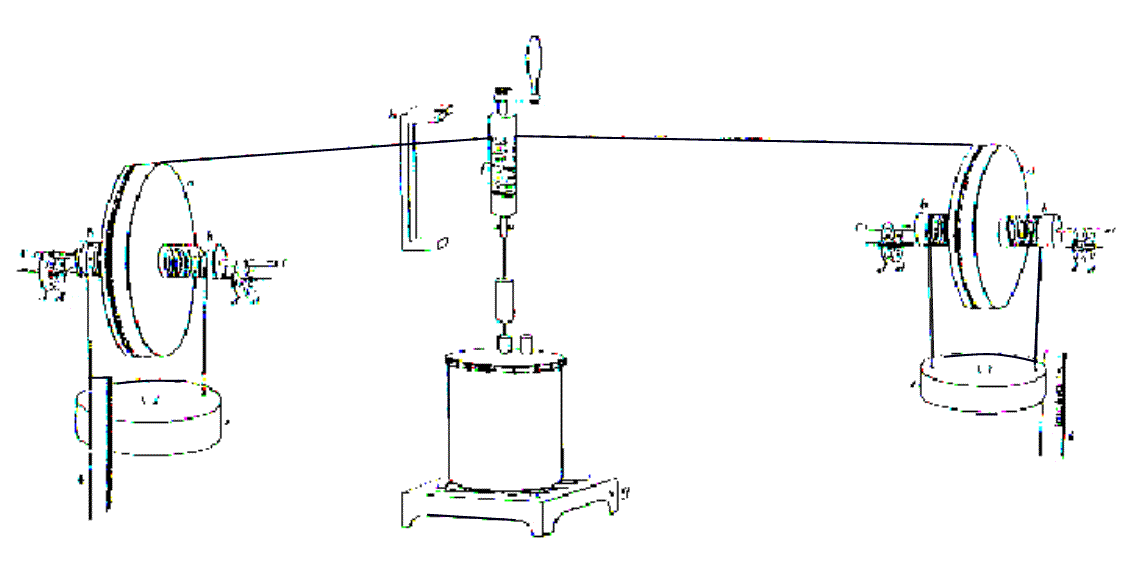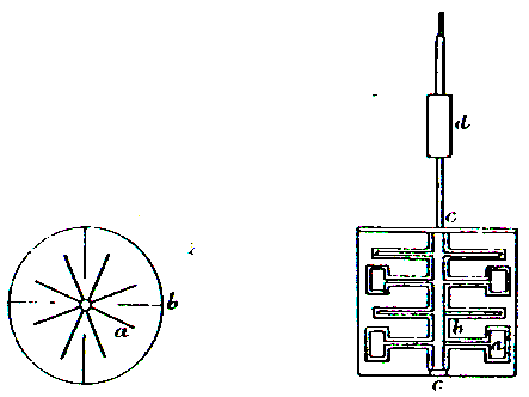実験4.力学的仕事の熱への転化
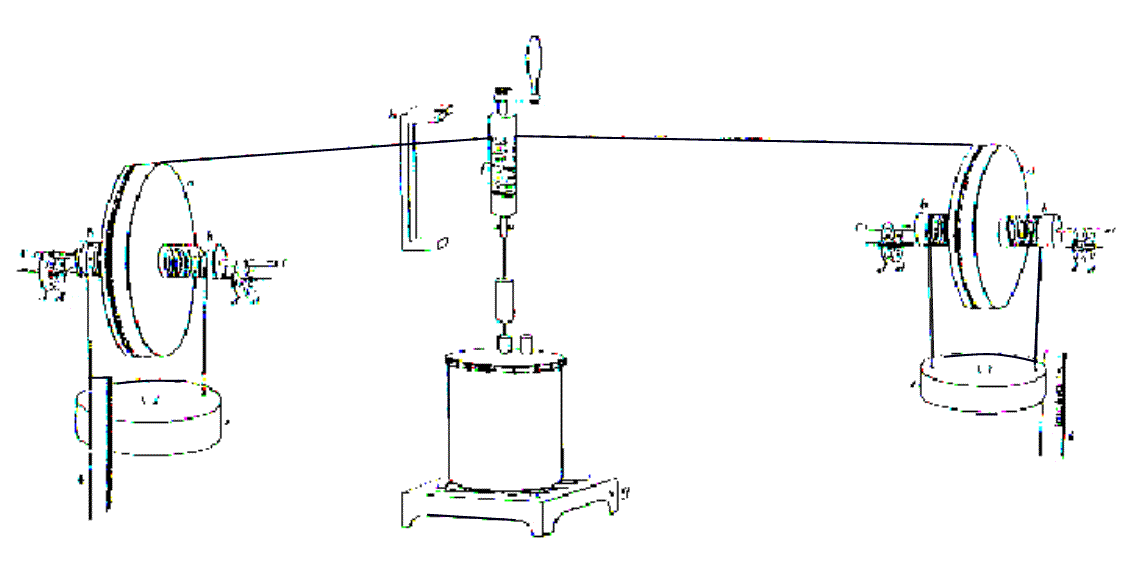 |
左図のような装置を用いて、羽車で容器の水
をかきまぜ、そのときの容器内の水の温度変
化とおもりがした力学的仕事を測定した。
|
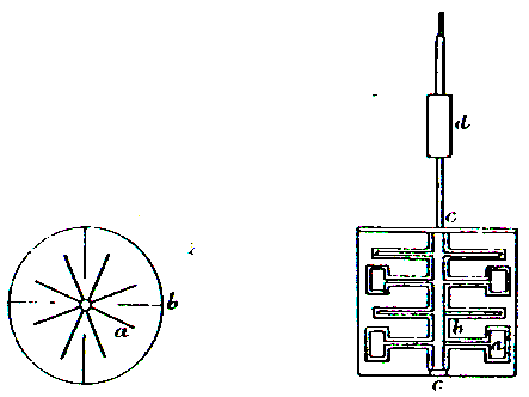 |
「水1ポンドにつき、 1F暖めるのに必要な
熱は、772ポンドの重りを1フートだけ持ち
上げる力学的仕事に相当する。」
|
Q10.水1ポンドを1F暖めるのに必要な熱量は何calか。ただし、1ポンド=453g、1F=5/9℃、水の比熱は1cal/g・Kとする。
Q11.実験4でジュールは、1calの熱は何Jの仕事に相当するという結論を得たか。ただし、1フート・ポンド=1.36Jとする。
1843年7月ジュールは実験2の研究報告を英国科学協会の化学部会(The Chemical
Section of Mathematical and
Physical Science of the British Association)で発表した。この論文は次のような書き出しをもって始められている。
「磁電機械(magnetic electrical machine)によって起こされた電気の力が全回路を通じて、他の電源から得られ
る電流と同じ熱的効果をあらわすことは広く認められているところであると思う。実際、熱を物質としてではなく、
振動の状態として考えれば永久磁石の2極の前で針金のコイルが回転するというような単純な機械的な作用に
よって熱が生起されないという理由はないと思われるのである。」
さらにジュールはこの論文に後記を付し、ランフォードの「砲身旋削」の実験に関して、
「ランフォード伯が大砲の穿孔(せんこう)にによって発生した熱を、摩擦によるものであって金属の熱容量による
ものではないとしたのは正当であった。」
と記すとともに、左記の実験以外にも力学的仕事の熱への転化実験を行い、その結果について次のように報じている。
「細い管に水を通すと熱が発生することを実験的に証明した。」
ここに電流を媒介とせず、力学的仕事が直接熱に転換される場合について実験が行われ、その定量的関係が求められたのである。
その後もさまざまな方法で熱の仕事当量の測定は続けられ、
最終測定(1870年)においては水中で羽車を回す方法で水1ポンドにつき、773.492フィート・ポンド/Fの値を得た。
すなわち、熱の仕事当量J[J/cal・K]とすれば、この結果より1フート・ポンド=1.36J,
1F=(5/9)℃,1ポンド=453gとして計算すると、
J=(773.429×1.36)÷(5/9)÷453
今日正確な測定によれば、熱の仕事当量は
であることが知られている。
ジュールは、前記の実験1〜4を通して、化学的エネルギー、電気的エネルギー、力学的エネルギーが「熱」へ転化することを見てきた。
1847年4月28日「物質、活力、および熱について」(On Matter,Living
force,and Heat)と題する講演において、彼はエネルギー保存の法則を明確に述べている。ここにそれを引用する。
「活力が見かけ上消滅するときには、いつも時の経過につれて再び活力に変わり得る当量のものが生み出される。
実験の示すところによれば、活力が見かけ上、消滅または消失するときにはいつも熱が生じるのである。」
ここでジュールの言う活力とは、運動エネルギーのことである。また、ジュールの言葉の逆の過程も成り立つ。
たとえば蒸気機関や空気の膨張は熱が力学的仕事に変わる例である。こうしてジュールは次のように述べる。
「こういうわけで、活力は熱に転化され、また熱は活力またはそれと等価な空間引力に転化される。
したがって、この三つ(熱と活力と空間引力)は、相互に転換し得るのである。この転化において何物も失われることはない。
熱の同一量はつねに活力の同一量に転化されるのである。」
ここでジュールの言う空間引力とは、今日の位置エネルギーのことである。さらにジュールは、上の命題を自然現象一般にあてはめ、下記のような一般的命題を帰納する。
「実に自然の諸現象は、機械的なものであろうと、化学的なものであろうと、また生命現象であろうとも、そのほとんどすべてが、
空間引力と活力と熱との間の不断の相互転換である。こうして宇宙に秩序が保たれる。 何ものも乱されず、何ものも失われることなく、
このように入り組んだ全機構が円滑に調和的に動くのである。」
これまでエネルギー保存の法則が発見される過程をジュールを中心に歴史的にたどってきた。ここで現代に戻り整理すると、
「エネルギーにはいろいろな種類があり、互いに移り変わることができる。そのときある種類のエネルギーが減った分だけ、
必ず他の種類のエネルギーが増加する。したがって、すべての種類のエネルギーの総和は、外部とエネルギーのやりとりをしないかぎり不変である。」
Q12.実験1、実験2の場合について、化学的エネルギー、電気的エネルギー、力学的エネルギー、熱エネルギーの転化について書け。
実験1.( ) → ( ) → ( )
実験2.( ) → ( ) → ( )
Q13.実験4では、どういうエネルギーの減少が、熱エネルギーに変わったのか。
6.エネルギー保存の法則成立の思想的背景
これまでジュールの行った実験をたどりながら、エネルギー保存の法則が成立されるまでの様子を歴史的にたどってきた。しかしながら、ジュールが何故あのように精密で根気のいる仕事を成し遂げることができたのかについての説明はほとんどなっかた。ここではジュールと彼を支えたユダヤ・キリスト教的価値観との関連を考えてみたいと思う。
科学史の具体的発展においては、実験や観察の諸事実あるいはそれらの単なる集積が新しい理論を導き出すのではなしに、むしろ既存のある概念の潜在と先行のゆえに、これらの諸事実を通して、科学的に未知な領域にかかわる理論や法則が見いだされたり、新しい科学概念が構成されていくという場合が決して少なくない。ジュールの場合にも先行概念として、ユダヤ・キリスト教的価値観があったと考えられる。
ユダヤ教およびキリスト教においては、神は唯一の創造者であり、人間をはじめ万物は、そのすべて被造物であって厳然たる区別がある。したがって、裏を返せば、被造物にはそのような創造も、また創造されたものを消滅させることもできないということである。それは、できるとしても、ただ等価的に変換することが許されるのみである。ここに、量的に厳密さをもった正確な代価という概念が成立し、それだけの代価を支払うことなしにそれだけのものを入手することはできないという認識が生まれるのである。これがすなわち、ユダヤキリスト教的価値観であり、代価の思想である。
ジュールは1844年の論文「空気の膨張および圧縮による温度変化について」の冒頭において次のように述べている。
「電磁エンジンの動力は、これを駆動する電池内の化学反応熱を代価として得られるものである。」
この思考法はユダヤ・キリスト教的価値観に特有の代価の思想と全く共通である。また他の論文の中の後記で次のようにも述べている。
「わたしは時を失わずにこれらの実験を繰り返し、また進めていこう。基本的な自然力は創造者の命令によって不滅であり、機械的な力が消費されるときにはつねに必ずそれに相当する熱の正確な当量が得られるということを確信するがゆえに。」
さらにジュールは、はじめて全面的にエネルギー保存の法則を表明した講演「物質、活力、および熱について」においても、次のように述べている。
「活力のこういう絶対的消滅が決して起こり得ないということは、演繹的に推論できるところである。なぜならば、神が物質に与えた力が壊滅すると考えることは、そのような力が人間の働きによって創造されると考えることにもまして不合理だからである。」
以上のようにジュールは、エネルギー保存の法則発見の下地として、宗教的な価値観をもっていたと考えられる。このような信念があったからこそ、あのような根気のいる実験を熱心に忍耐強く行い、この唯一の問題解決のために彼の生涯の大部分を捧げることができたのだと思われる。
Q14.ユダヤ・キリスト教的価値観(代価の思想)とは、どういうものか説明せよ。
Q15.「時は金なり。」「貧乏暇無し。」のふたつの諺でユダヤ・キリスト教的価値観が表れているのはどちらか。